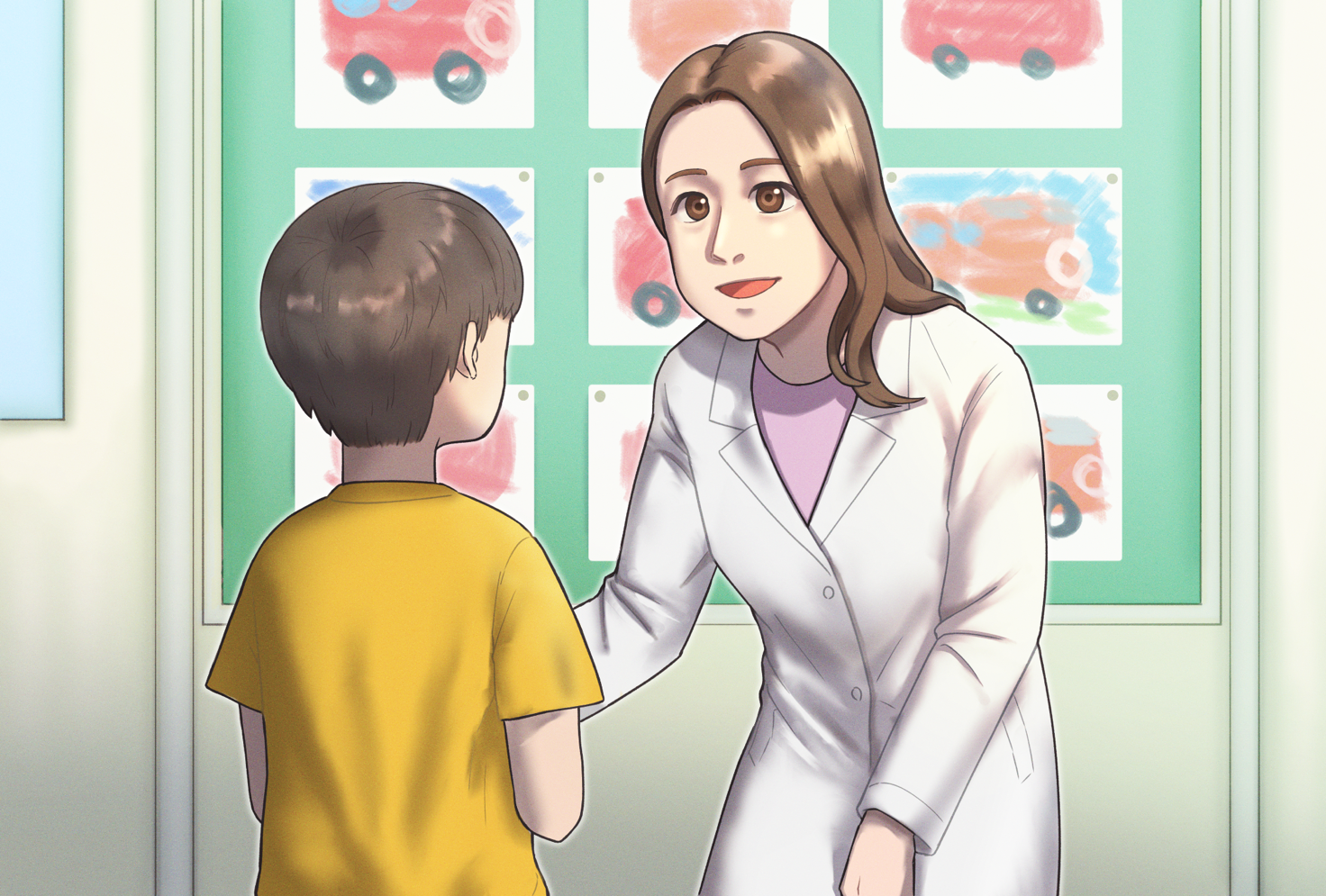- 原郁水
- HARA IKUMI
- [ 教育学部 教育保健研究室 准教授 ]
学校におけるレジリエンスの育成
今回は「学校におけるレジリエンスの育成」についての研究です。
みなさんは学校生活を過ごす中で、「友達と喧嘩をしてしまった」「テストで思うような点数をとれなかった」などの悩みを抱えることはありませんか?学校では授業や部活、行事への参加など、色々な人と関わる機会があるため、悩んだり落ち込んだりするのは、決しておかしなことではありません。しかし、落ち込んだときには、その困難から立ち直ることが大切です。困難から立ち直るときに働く力は、「レジリエンス」と呼ばれています。
そもそも「レジリエンス」とは?
「レジリエンス」は回復力や反発力を意味する言葉で、教育学や心理学の分野では「落ち込みからの回復を促す力」などと言われています。前向きに捉えられることや気持ちを落ち着かせられることも、回復の一種と考えられます。しかし、全ての人が同じように回復できるとは限りません。人それぞれ性格が違うように、持っているレジリエンスも異なります。
また、レジリエンスの中には、教育や経験、環境などによって変化するものがあります。自分がこれまでにどのような悩みを抱え、どのように立ち直ってきたかを振り返ることで、今持っているレジリエンスに気付けるかもしれません。
多くの子どもが立ち直れる力を身につけられますように
弘前大学の原郁水先生は、小学校の養護教諭として働いていた際、様々な理由で落ち込んでいる子どもに出会いました。その中には、時間をかけて落ち込みから立ち直った子どももいれば、立ち直ることが難しい子どももいました。
そこで、子どもたちみんなに立ち直る力を身につけてほしいとの想いから、原先生は学校でレジリエンスを高める方法について研究することを決意しました。
授業開発では、レジリエンスを高める授業の前後でアンケートをとり、どういう人のレジリエンスが高まっているか、どのようなアプローチがレジリエンスの向上に効果的かなどを調査・研究しています。その調査を基に学校で実践し、子どもに変化が現れるという結果が出ています。
学校は学習だけが目的ではない
学校では、学級活動や学校行事、部活動などの学習面を目的としない活動も数多く行われており、レジリエンス研究を通して、これらの活動の意義が分かるようになるという魅力があります。そして、レジリエンスが変化する理由や方法を見つけることは、子どもたちの健康的な成長発達に繋がります。
最後に、原先生からのメッセージ
私の研究室には、保健室の先生である養護教諭を目指していて、その中でも特に教育や心理に興味を持つ学生が所属しています。そして、それぞれの学生は自分が興味を持った疑問について研究をしています。レジリエンスに興味を持たれた方、学校教育における心の健康に興味がある方、ぜひ私たちと一緒に問いに取り組んでいきませんか。
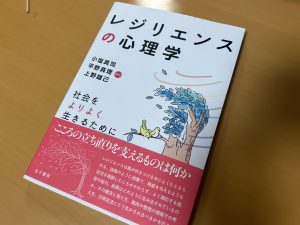
共著の書籍『レジリエンスの心理学』
陸奥新報社 2023年(令和5年)10月2日 掲載(PDF)
ライター:人文社会科学部3年 和田 桜佳
イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰
担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構