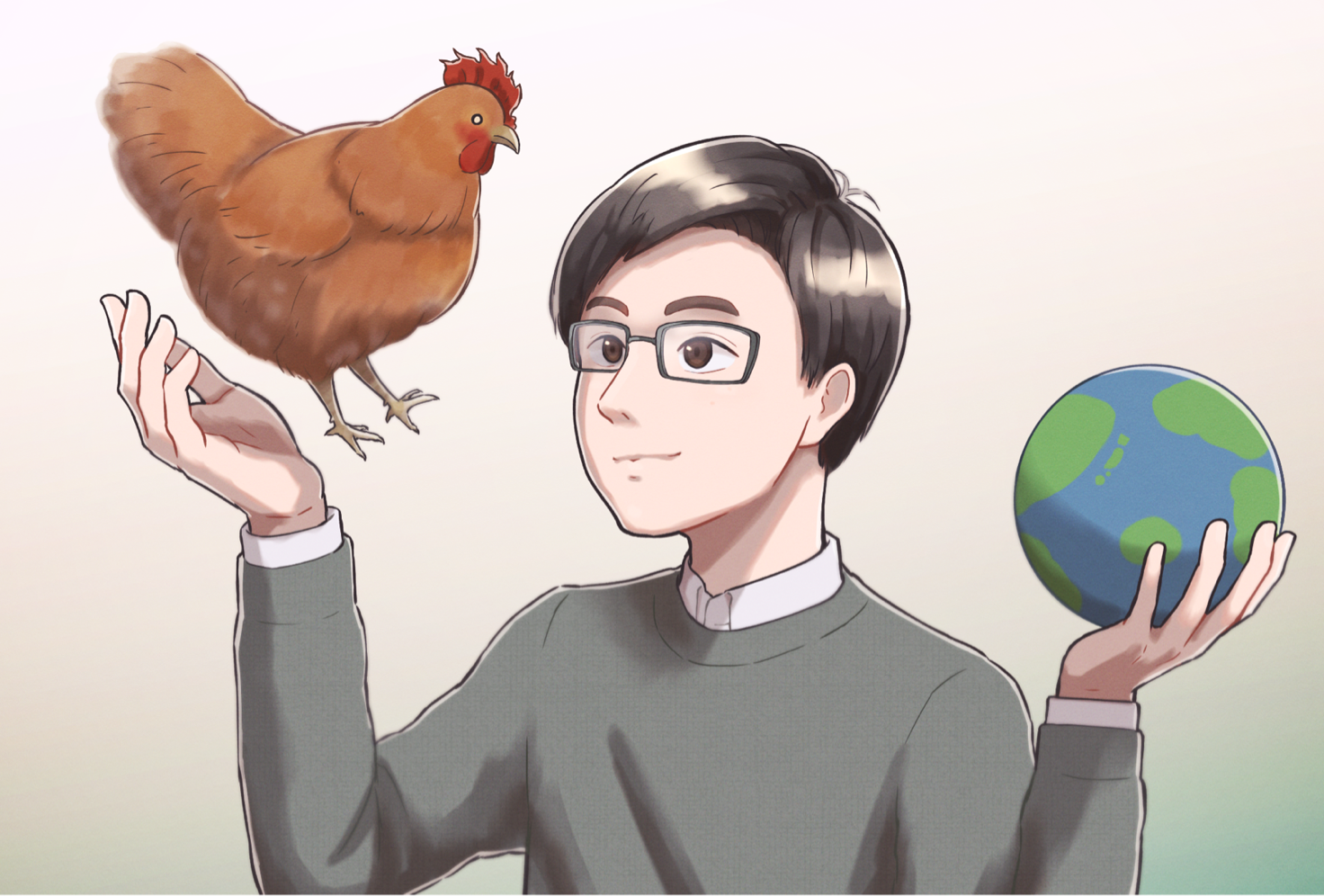- 川端二功
- KAWABATA FUMINORI
- [ 農学生命科学部 国際園芸農学科 家畜生理学分野 准教授 ]
味を理解している?ニワトリの味覚の研究。
探究心旺盛な小中高生の皆さんに向けて、弘前大学の先生たちのユニークな研究を紹介するこの連載。今年度からシーズン2に突入です。今回は「ニワトリの味覚」についての研究です。
皆さんの食卓にも並ぶ、美味しいたまごを産んでくれるニワトリ。実はニワトリも、エサを美味しいと感じたりすることを知っていますか?
ニワトリのエサといえば、粉のような飼料をついばんでいるイメージがありますよね。そんなニワトリも甘味、うま味、苦味、酸味、塩味を感じているのです。美味しいと感じたときは、ついばむ回数が増えたり、たくさんエサを食べたりします。逆に美味しくないと感じたときは、首を振ったり、食べ残したり、時には吐き出したりもします。
人間は味を感じるときに、舌の表面にある味蕾と呼ばれる味覚センサーから味を感じます。ニワトリの味蕾は舌の根元にも少しありますが、多くは上顎の内側である口蓋と下顎の内側にある口腔底にあり、そこで味覚を感じていることがわかりました。しかし、ニワトリの味覚の全体像についてはまだ明らかとなっていません。ヒトの味覚研究と比べて、研究が遅れているというのが現状です。
そこで、本学の川端二功先生はニワトリの味覚に着目し研究をしてきました。ニワトリは地球上で最も生息数が多い鳥で、宗教上の制約が少ないことから今後も世界的に需要が増えていくと予想されている産業動物です。
未利用資源から新しい飼料の開発が可能に。
川端先生の研究から甘味等の基本的な味の他にも、ニワトリは油脂の味や、カルシウムの味をキャッチできるセンサーを持っていることがわかってきました。ニワトリの味覚の研究が更に進めば、エサの食べ残しを減らしたり、これまで資源として使われなかった未利用資源を好ましい味に変化させ摂取させたりすることが可能となります。こうした飼料の開発は、地球環境への負担を減らすことに繋がり、家畜飼料の多くを輸入している日本にとって大きなビジネスチャンスに繋がります。
最後に、川端先生からのメッセージ
研究は、疑問を持つこと、その疑問を論理的に粘り強く解決していくことが大事です。今からその力を身につけてほしいと思います。
ニワトリの味覚の研究は世界を変えるところまできています。新しい飼料の開発は、地球環境の面から考えても世界のサプライチェーンに大きな影響を与えます。まだまだ珍しい研究分野なので、世界の第一人者になれるかもしれません。研究に魅力を感じた皆さんと、研究室でお会いできる日を楽しみにしています。
 ロードアイランドレッド種(ひな)の食餌風景
ロードアイランドレッド種(ひな)の食餌風景
陸奥新報社 2022年(令和4年)4月25日 掲載(PDF)