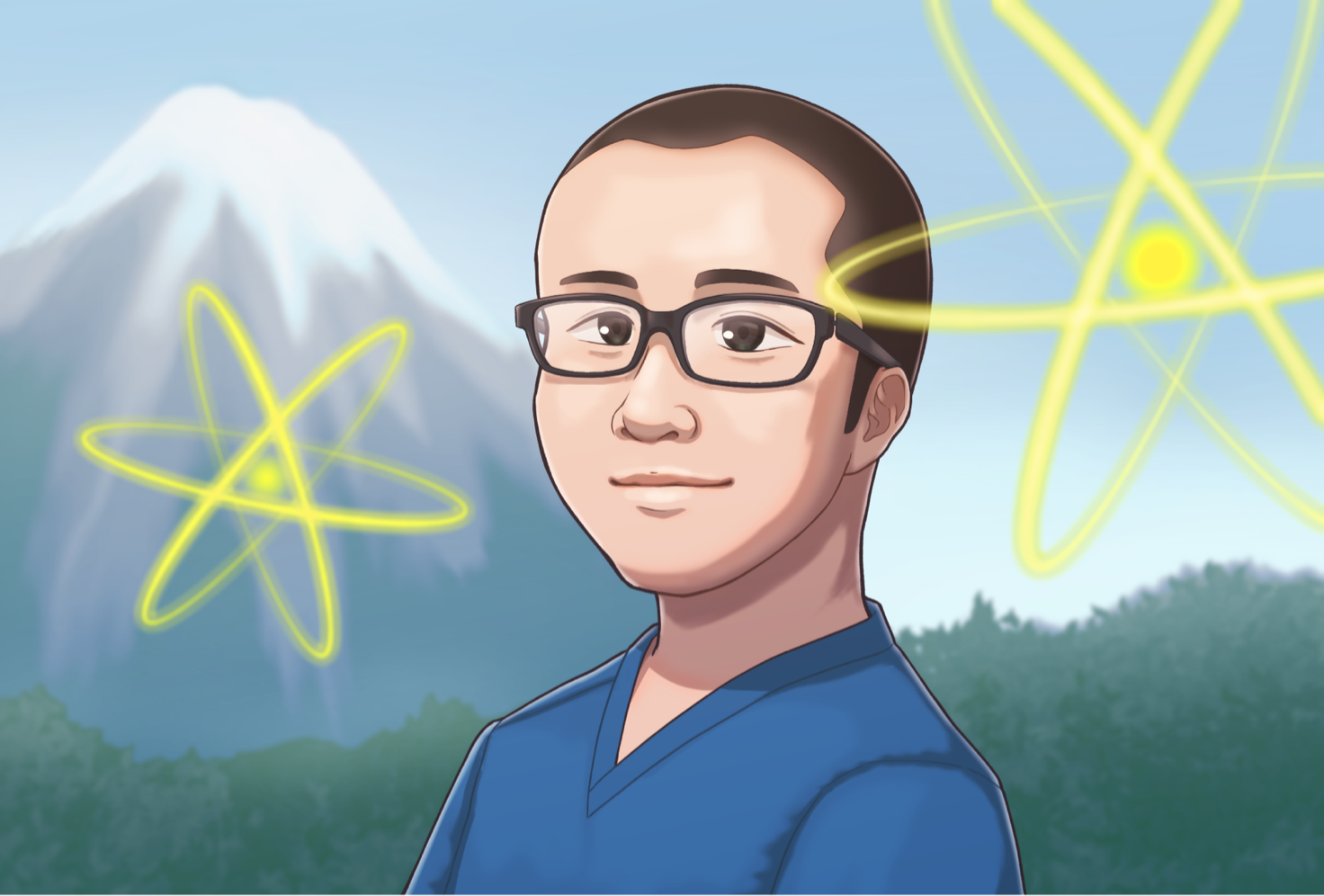- 細田正洋
- HOSODA MASAHIRO
- [ 保健学研究科 放射線技術科学領域 教授 ]
ラドンはどこからやってくる?
実は、私たちの身近にある放射線。
探究心旺盛な中高生の皆さんに向けて、弘前大学の先生たちのユニークな研究を紹介する連載。今回のテーマは、「放射性物質 ラドン」です。皆さんは、私達の身のまわりにさまざまな放射線が存在していることを知っていますか?
放射線は五感では感じませんが、たとえば、宇宙からは放射線の一種・宇宙線が降り注ぎ、大地からも放射線が出ています。また、食べ物や飲み物、呼吸によっても放射性物質を取り込み、そこから放射線が出てきます。
自然界にある放射性核種のなかには、ラドンがあります。ラドンは、土壌や岩石に含まれているラジウムから作られ、地上に出てきます。
世界保健機関(WHO)によると、ラドンは呼吸によって肺の中に取り込まれることで、たばこに次ぐ第2位の肺がんの原因となることが明らかになっています。そのため、最近では欧州を中心に肺がんの潜在リスク地域を推定し、マッピングをする研究が行われています。
身近な放射線被ばくから人々を守るために
「弘前大学被ばく医療総合研究所」を有する本学は、世界から注目を集める放射線研究の拠点。保健学研究科の細田正洋先生は、ラドンがどこから来て、私たちの生活環境中にどのように放出されるのか、そのメカニズムを研究しています。
土壌表面からのラドンの放出量を測定するためには計測器を用います。細田先生たちは、従来の装置に比べてコンパクトで軽く、かつ短時間で計測できる計測器を開発しました。将来はこの測定器を使って、日本初のラドンによる肺がんの潜在リスクマップを作成する予定だといいます。
そのほか、先生は、鹿児島県桜島などで土壌表面からのラドンの放出量を測定し、火山活動との関連性も調べています。新しい放射線計測技術を利用することで身近な放射線被ばくのリスクを軽減したり、自然現象の解明に役立てることができるんですね。
最後に、細田先生からのメッセージ。
自分の専門分野だけでなく、地質学や気象学などなどさまざまな分野の専門家と一緒に研究することで、まるでパズルが解けるように要因が解明できることもあり、それが面白いなあと思います。皆さんも日々の生活のなかで「なぜ?」と思う気持ちを大切にしてください。そして、自ら調べることで得た情報のなかから何が正しくて何が間違っているかを見極める眼を養ってほしいと思います。

可搬型ラドン測定装置
陸奥新報社 2022年(令和4年)2月7日 掲載(PDF)