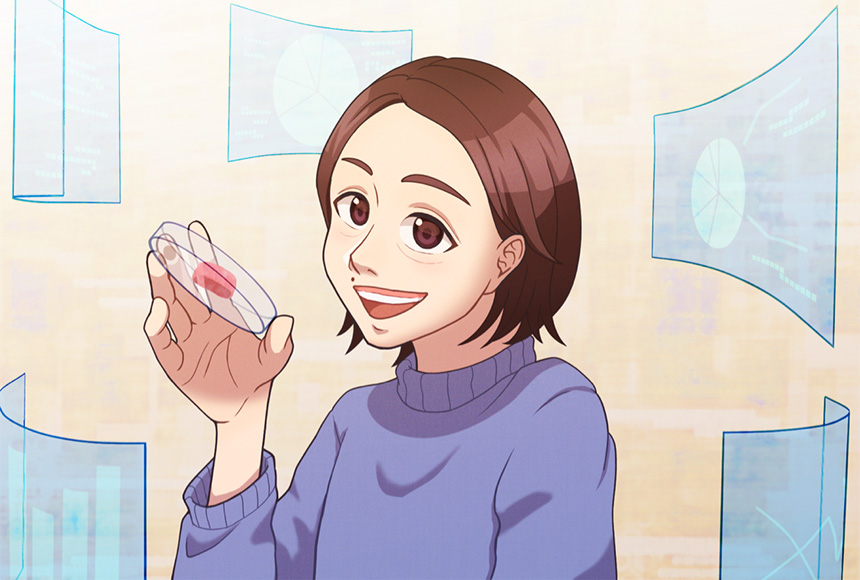- 日比野愛子
- HIBINO AIKO
- 専門 社会心理学
- [ 人文社会科学部 社会心理学研究室 准教授 ]
[ 大学院地域共創科学研究科 ]
探究心旺盛な、中高生のみなさんへ。
中高生の皆さん、毎日の暮らしの中で「なして?」と思うことはありませんか?「なして?|は探究心の小さな小さな芽のようなもの。それを大切にしてほしいという願いと共に始まるのがこの新連載です。毎回、弘前大学の先生たちが皆さんと同じような「なして?」の気持ちで取り組んでいるユニークな研究をご紹介。面白い題材やテーマが次々出てきますのでお楽しみに!
日常あるある!がいっぱい。私たちのくらしに身近な社会心理学。
皆さんは、「社会心理学」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか?なんだか難しくて自分とは関係なさそう…。そんなふうに感じるかもしれませんね。社会心理学は、人の心理や行動をもたらす、その背後にあるものを研究する分野。実は私たちの日常と深く関わっているのです。
たとえば、まわりの意見や行動に合わせて自分も同じように行動してしまう「同調行動」、美人やイケメンを見ると、きっと頭や性格も良いに違いないと、ある一つの要素によって全体を高評価してしまう「ハロー効果」。また、家庭ではとてもおしゃべりな人が、学校では無口になって“キャラ愛”してしまうなど、関わり合う集団や場所によって違った行動をとることもあります。皆さんも、思い当たることはありませんか?
「培養肉」に関する意識調査。異なる意見を持つ人の背景を探る。
本学の日比野愛子先生は、「新しいテクノロジーが登場したときの人々の反応」について研究しています。近年は、「培養肉に対する社会心理の研究」に取り組んでいます。
SDGs(持続可能な開発目標)に注目が集まる中、今、世界では、牛などの細胞で作る「培養肉」の技術開発が進められています。
しかし、こうした新しい技術が登場する時には、賛成の意見も反対の意見も出てきます。日比野先生は、培養肉研究に取り組んでいる東京大学や日清食品ホールディングス株式会社と共に、「培養肉に関する大規模意識調査」を行いました。
その結果、「培養肉を試しに食べてみたい」と考える回答者は3割弱でした。そして、培養肉に賛成する人は、細胞や人工知能など、私たちが普段生物だと思いにくい曖昧な対象でも「生物だ」と考えやすいことが分かりました。
このように、社会心理学の調査では、単に賛成・反対の数をしるだけではなく、異なる意見を持つ人の背景に注目し、どうしたら課題解決につながるのかを探ります。そのため、社会心理学を学ぶことで人間関係だけでなく商品企画やマーケティング、組織運営などビジネスシーンにおいても効果を発揮する場面がたくさんあります。
最後に、日比野先生からのメッセージ。
「身近な生活のなかで、何か引っかかったり疑問に感じたことは社会心理学の重要なテーマ。どんな些細なことでも掘り下げてみると面白いですよ。自分と異なる意見を否定するのではなく、相手がなぜそう考えたのかバックグラウンドに注目してみてください」。
陸奥新報社 2021年(令和3年)7月5日 掲載(PDF)